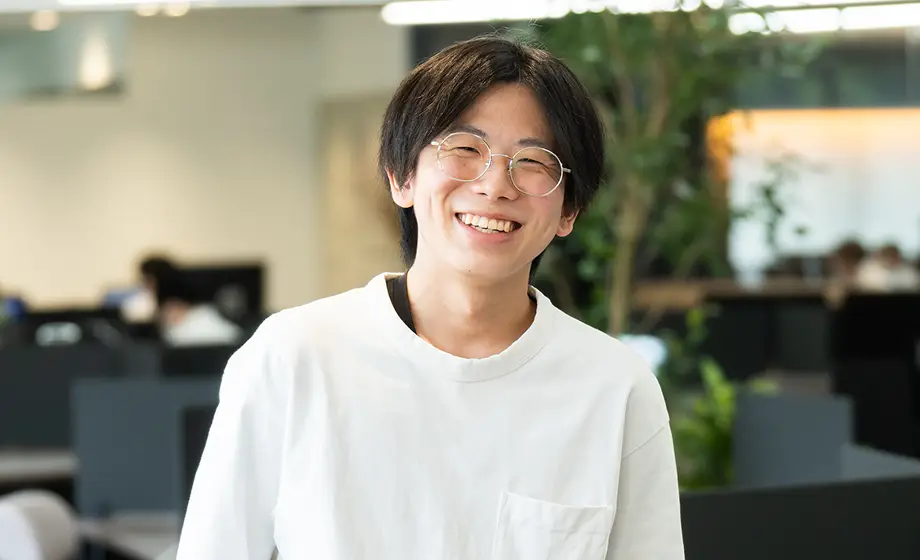社員インタビュー
ユーザーへの価値提供を
モットーに、社外での
学びを社内に還元
Nobuhiro エンジニア / 2022年 中途入社
バンドルアプリ、Webサイト、官公庁の大規模システムなど、約17年ほど幅広くQAプロジェクトに従事しています。社外活動としてSQiP研究会*1で2年間レビュー分科会に所属し品質を学んできました。これまでの経験を活かし、現在はマネジメントを主な業務とし、プロジェクト推進、チーム形成に努めています。
*1…https://www.juse.or.jp/sqip/workshop/

Q1. キャリアのきっかけ
時代×スキル
20代後半までは全くの異業界で働いていて、時代の変化に伴って「廃れない仕事」に就きたいなと考えていたところ、IT業界に興味を持ちました。「インターネットがこの世から必要とされなくなることはないだろう」と思い、情報収集した結果、さらに必要不可欠な存在だと感じた第三者検証事業を展開している企業に入社しました。その後10年ほど、映像系のソフトウェアテストを中心に、さまざまなプロジェクトに参画しました。着々と経験を積んでいる実感を得ていましたが、とある新しいプロジェクトに参画することになった際に、「はじめて聞くテスト技法だ…」と自身のスキルを過信していたことに気づいて危機感を覚えたことを鮮明に覚えています。とはいえ、何から勉強していいのかわからず焦燥感を覚えていたところ、当時の上司にSQiP研究会を紹介してもらったのです。

Q2. 社外活動での取り組み
外の世界で気づいた価値観
SQiP研究会には5つの研究会があり、私はレビュー分科会に参加しました。この分科会では、早期に不具合を発見できる手段として用いられる「ソフトウェアレビュー」について、参加メンバーが自身の現場課題を共有し、効率的・効果的なレビューを行うための工夫やノウハウを得て、レビュースキルを向上させるテクニックを学びます。他社のエンジニアの方々と一緒に基礎から学び、最終的には論文を発表します。最初はわからない単語が飛び交い過ぎて、月に一度メンバーと集まって分科会活動を行うものの、彼ら・彼女らとの共通理解を生むことが最初の難関でした。ソフトウェアレビューに関する書籍をたくさん読み込み、分科会でアウトプットし、その繰り返しを行うことで得た学びを活かして論文を2つ発表*2しています。
自身のインプットを論文として残せた喜びはもちろん、この経験を活かし、アジャイル開発のプロジェクトでテストマネージャーを務め、官公庁系のプロジェクトでのPMなど、大規模プロジェクトに従事することもできました。自身のステップアップにつながったと同時に、QAという世界の広さを知ることができた期間でした。より高い品質を求めるには、もっと視野を広く持ち、QAという上位概念から工程を考えなくてはいけません。それまでは自身のことを「テストする人」と認識していましたが、QAはテスト工程でただ不具合を潰していく役割ではなく、開発工程全体を俯瞰して、不具合発生を未然に防ぎ、品質を底上げする存在だと思います。知識・経験0でこの業界に飛び込んだ17年前のあの頃と比較して、たくさんの学びを得て、価値観新たにできたことで、よりQAという仕事が好きになりました。この経験は自分の中だけに留めることなく、今でも一緒に仕事をするメンバーと共有して大切にしている考えです。
*2…2014 重大欠陥を早期是正するレビュー手法 3分割レビューの提案
…2015 欠陥パターンと検出テクニックを用いたレビュー手法の提案

Q3. QAエンジニアとして大切なことは?
自分の仕事が1番ではない
AGESTには、2022年にジョインしました。現在はプロジェクトの第一線からは離れ、グループリーダーとしてマネジメントを主な業務としています。お客様の要件・課題を理解したうえで、参画メンバーを検討したり、スケジューリングをしたり、プロジェクト品質を高めることに注力しています。そんな今でも大切にしているのは、「エンドユーザーに価値を提供することが最優先」であるということです。やはり品質を追い求めると、QAエンジニアの性分として、とことん不具合を潰したくなってしまいます。もちろん、それを叶えることも大切ですが、時間や予算を考慮すると、中々難しいシチュエーションもあります。エンドユーザーが使ってみて初めてそのモノの価値が生まれ、さらに良いモノにするための知恵が出てきます。自分のこだわりやプライドは一度脇に置いて、自身の仕事のベクトルに柔軟性を持たせることを、今後も意識していきたいです。